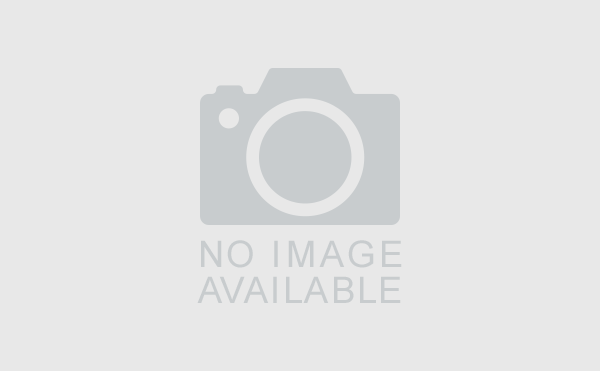私たちの多くは、自分のことを良く分かっていません。
ほとんどの場合、言葉にされている以上の感情や思いが必ず内面に存在します。
「イライラするけど、何に対してかよくわかっていない」
「モヤモヤするけど、ハッキリ何が嫌なのか分からない」
私たちカウンセラーは、表面にあらわれている現象や、言葉や態度、行動の裏に隠された、
本当の感情や望みを丁寧に紐解いていくことが大きな1つの役割です。
原因が分からなければ対処できません。対処できなければ問題は解決されません。
自己理解が進めば進むほど、自分の問題に自分で対処する力もどんどんついていくのです。
対処する方法は、必ずしも1つではありません。
立ち向かう、自己主張する、断る、無視する、逃げる、人に頼る、休む。
特に頑張りすぎて潰れてしまう人は、
『断る、無視する、逃げる、人に頼る、休む』という選択肢が取りにくいことが多いです。
優しくて、頑張り屋さんで、自己犠牲や責任感が強いんですね。
でも、「あるべき(と思っている)姿」と「ありたい姿」は、まったくかけ離れたものだったりします。
人生は、選択の連続です。
そして、自分以外の他人や事象をコントロールすることはできない中で、
自分にとってのベストを選んでいくことが大切です。
色々な方法がある中で、社会や他人の声に振り回されず、
自分の心が本当に望むこと、
自分で自分を幸せにするために必要なことを、適切に選んでいくためには、
自分の本当の気持ち、自分が心から望むものを、自分できちんと理解する必要があります。
強い強迫観念のような衝動の正体は?
特定の選択肢を取ってはいけないような、または取り続けなければいけないような、
強迫観念に近い感覚を持っている人がいます。
そんなの負けだとか、ずるいことだとか、不誠実だとか、不適切だとか、大人げないとか、
様々な社会理念や倫理観、しつけの影響があります。
交流分析という心理学においては、そういったことを『人生脚本』として表現されています。
事例として分かりやすく、私が見つけた自分自身の人生脚本の一部をご紹介します。
今日は、その一部である【ドライバー】という概念について説明したいと思います。
私たちを駆り立てる【ドライバー】とは?
ドライバーとは、親や環境からの繰り返しのメッセージで形成される、いわば愛されるための「生き残り戦略」です。
私たちはみんな、本当は自分を愛してほしいものです。
ドライバーに突き動かされている人は、「条件付きでないと愛されない」と、心の奥底で無意識に感じています。
この、『条件』にあたるものが、ドライバーだと思ってもらっていいでしょう。
『ドライバー:駆り立てるもの』という名称の通り、
私たちに「~でなければならない」「~でないと愛されない」と、強い衝動を与えます。
5つのドライバーと、私の場合
Be Strong(強くあれ)
誰にも頼らず泣き言も言わず1人で頑張り続けてきた忍耐強い母。
「愚痴を言うならやめなさい」「弱音を吐くならやめなさい」と、
自分の決断に責任を持つことを教えてもらい、
「泣いてはいけない」「弱音を吐くな」というメッセージを受け取りました。
Please Others(人を喜ばせよ)
そんなに記憶にはなかったのですが、幼少期を客観的に振り返ると、
とにかく父の闘病看病や事業の継続で忙しそうにしていた母や周囲に、
また、父の死後は1人で子供たち4人を働きながら育てるという多忙な母に、
心配や迷惑をかけないように、常にいい子でいたかったのだと思います。
「父や母が喜ぶ選択をする」という価値・判断基準が、当時は染みついていましたね。
「手のかからないいい子だった」とはよく聞かされていました。
また、兄の反抗期に涙を流す母を見て、「母を悲しませてはいけない」と、強く刻まれたのだと思います。
そのドライバーが、他者に対しても働き、
「ガッカリさせてはいけない」「悲しませてはいけない」というベースになり
自分を追い詰めたり自己否定する原因となっていました。
Be Perfect(完璧であれ)
兄に比べ成績も素行も良く、
「お前は何の心配もいらない」「いい子だね」「自慢の孫」と
母や祖母などまわりの大人から褒められ、
学生時代から、勉強・生徒会・部活でキャプテンなど
「ちゃんとできる子」である必要性を強く感じていました。
アナ雪のエルサも、この「いい子でいなければならない」がかかっていて、
求められている理想像と本当の自分とのギャップに、苦しんでいましたね。
主題歌 Let it Goの「The Perfect Gir is Gone(完璧な女の子はいなくなった)」という歌詞は
映像も相まって、『いい子象』を脱ぎ捨てるというとても象徴的な名シーンだと思います。
Try Hard(努力せよ)
努力家だった父のストーリーを何度も聞かされ、
頑張ることがいいことだと思っていました。
ドライバーが強すぎたので、
いくら頑張っても、いくら評価されても、まだまだ足りない気がして、
十分頑張っていても、些細なことで自己嫌悪というパターンが何度も出ていました。
Hurry! (急げ)
「早くしなさい!」
学生時代から一番母から言われた言葉No.1は、おそらくこれです。
ワンオペで誰に頼ることもなく、
いつも時間に追われせわしなく家事に育児に仕事にこなしていた母から常に急かされ、
「ゆっくりすることはダメなこと」と身に付きました。
母自身にもこのドライバーは強くかかっていたと思います。
私は日本を出て時間の概念が日本よりも緩い環境に身を置いたことで
自然に緩まったと思います。
環境や周りの人間がアロワー(許すもの、緩めるもの)となって、ドライバーを緩めてくれることはよくあります。
SNSなんかを見たり友達の言動を見て、
「え、こんなことしてもいいんだ!」「これでも許されるんだ!」と視野が広がった経験は、
あなたにもあるのではないでしょうか?
ドライバー自体は必要なもの。問題なのは、生きづらさ。
ドライバーとはいわば、脳内に響く他者の声です。(親の声や社会、常識、世間)
ドライバーはある程度は全員が持っているもので、
社会規範や秩序を守るため、良好な人間関係を築き自己実現へ向かうために必要なものです。
問題となるのは、ドライバーが強くかかりすぎて、支配されている状態です。
自分の本当の気持ちや欲求とは裏腹の行動を続けることになりますので、
負担が蓄積されストレスが溜まり、人間関係のトラブルやメンタル崩壊につながります。
その場合は、自分のドライバーに気付き、意識的に緩めることがとても有効です。
私に強くかかっていたドライバーと、その発端は?
最初に交流分析を勉強したころは、私には「強くあれ」以外のドライバーが強くかかっていると思っていましたが、
その後自己理解が更に深まるにつれて、「強くあれ」も、結構強かったのかも、と思いました。
幼少期の父との記憶はごく限られていますが、
はっきり覚えている記憶として、父が亡くなった日と、父の葬儀の日です。
葬儀の場で、悲しそうな顔をしている参列者に、やり場のない怒りの気持ちが湧きました。
「一番悲しいのは私たちなのに、誰なのこの人たち!この人たちにとってのお父さんは何なの!」というような、とても子供らしい素直な怒りでした。
涙をこらえながら対応している母を見て、私はなぜか泣けず、トイレにこもって強く怒りながら泣いたことを覚えています。
母や祖母、兄など大人に寄り掛かることもなく、見えないところで1人で泣いたという選択から、
あの時点で「強くあれ」というドライバーがすでに強くかかっていて、更に強化されたと想像できます。
誰かに寄り掛かること、例えば誰かの胸で泣く等は、とても強い抵抗や違和感を感じていたことを思うと、
「強くあれ」のドライバーはある程度私の中に強くかかっていたのだと思います。
今でも、映画や別れの場面、悲しいときや悔しい時には、
泣いている自分を見られたくない気持ちがあります。(感動して泣いた、や、嬉しくて泣いた、はOK)
また同時に、自分の感情を抑えて他者を優先することと、
怒りを感じることをやめるという決断も、ここで強化されたのかなと思います。
それが当時、私にとっての、辛い気持ちや大きな喪失感から、自分を防衛するための、生存戦略だったのでしょう。
そう思うと、私にも「強くあれ」のドライバーも結構強くかかっていたなと感じますが、
おそらく成長の過程でたくさんのご縁に恵まれ、温かい人間関係の中で、緩められてきたのだと思います。
また、「強くあれ」以上に、「完璧であれ」や「喜ばせよ」のドライバーが強くかかっていたこともあったのかもしれません。(悲しんでいるお母さんを困らせてはいけない、心配させてはいけないという気持ち)
※脚本は3歳ごろには形成され、10歳頃までの経験を経てある程度固まったものになると言われています。しかし内容の強度によっては、それ以降の経験も大きく影響されますので、20歳くらいには完成していると考えていいと思います。それ以降の経験は、脚本に沿って行動・選択し、脚本の正しさを証明するかのように、脚本(=認知の歪み)が強化されていきます。
最後に・・・
長くなってしまったので、今日は一旦ここまでにしますね。
次回は禁止令について書こうと思います。
自分のドライバーに気付くことの重要性と注意点
人生脚本やドライバーは少し抽象的で分かりにくい概念なので、
誰かの具体的な事例を読むことで、
「自分もこういう経験から、こういうドライバーがかかっていたかもしれないな」と、
ご自分を振り返るきっかけになるかもしれないなと思い、共有することにしました。
過去を振り返るとつらい人、思い出すだけでしんどい人は、無理に深堀しないでくださいね。
過去や原因に触れなくとも、今の自分の行動・選択する際の判断準や大切にしている価値観を客観的に観察し、
自分のドライバーを見つけることで、緩めることは可能です。
まずは自分で気づくこと。そしたら意識して、緩められます。
そして、「このドライバーがかかっていそうだな?」、と思うものが見つかったら、
「このドライバー(価値観)は、今の私にとって、こんなに強くかかっている必要はあるか?」
「この通りにしないと(条件)本当にダメなのか?」
「本当に、私が心からやりたいことは?」
と、自分に問いかけてみてください。
ドライバーを見つけるヒントは、頭で考えるだけでなく、心でも感じることです。
抽象的な表現になりますが、本当に自分が望んでいることは、頭ではなく心が知っています。
具体的に言うと、「自分がどのような感情になっているか?何があるから?」を、
1層2層と表面から皮をめくっていくように、何度も何度も自問自答してみるのです。
長年本当の感情を奥に押し込んできた人ほど、
この過程は本当に丁寧に、ゆっくりとやらないと、すぐに思考に邪魔されます。
その方が楽で、簡単で、安心するからです。
でも、慣れ親しんだ習慣=幸せな生き方とは限りませんよね。
そこを打ち破るための小さな一歩を勇気を出して踏み出すことで、
大きく人生が変わっていくこともあるんですよ!
是非、自分のドライバーに気付き、
強すぎるものは緩め、ご自身にとって心地の良い、気分の良い、幸せな選択を
自分の責任で、自分の意志で、取捨選択していってくださいね。
もちろん、私たちの人生は交流分析の概念だけで語りつくせるほどシンプルなものではありません。
その背景には1つではなく様々な理由は要因が複雑に絡み合っています。
しかし、こういった概念を知ること、心理学的な知識を得ること、
そしてそれを通して自己理解を深めることは、
私たちの幸福度やメンタルヘルスの向上に直結していると、私は信じています。
私の体験が、どこかで誰かの力になれれば嬉しいです。
では、また次回!
神田華子でした。